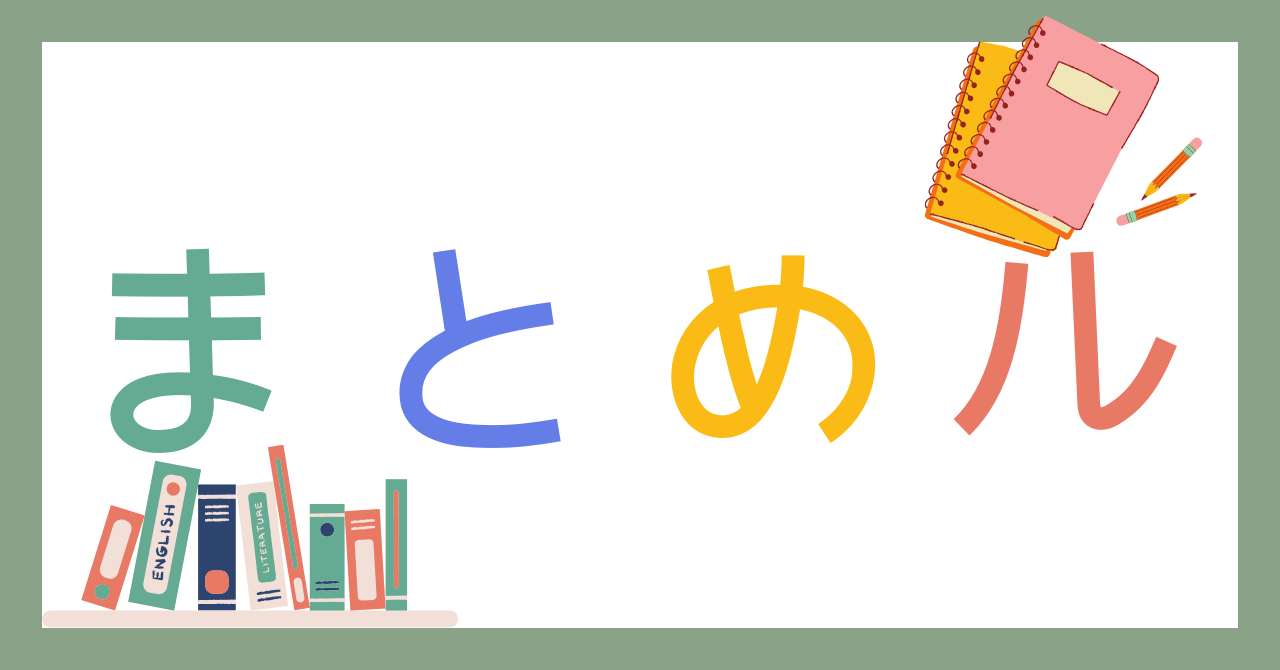備蓄米の販売期限が延長へ 引き渡しの遅れが影響
小泉農林水産大臣は8月中旬、備蓄米の販売期限を延長すると発表しました。
これは、備蓄米が消費者の手元に届くまでに時間がかかっている現状を踏まえた判断です。
備蓄米は、令和6年6月から8月末までの期間、随意契約により販売されてきました。
しかし、約28万トンのうち、10万トン以上がいまだ引き渡されていない状況にあります。
このため、販売を希望する業者などに向けて、引き渡しおよび販売の期限を延長する措置が取られました。
農水省が当初、販売期限を設けた背景には、新米の価格に対する影響を抑える目的がありました。
しかし小泉農水相は、「備蓄米が出回っても銘柄米の価格に大きな影響を与えた例は少なく、新米価格に影響する可能性は低い」と述べています。
各地で新米価格が高騰 過去と比べて最大1.7倍も
一方、2025年の新米価格は全国的に高騰しています。
福井県内のJA農協では、新米「ハナエチゼン」の初出荷が行われ、
JAが生産者に支払う概算金は前年の1.7倍となりました。
収穫量自体は平年並みとされていますが、価格が大きく上昇しています。
石川県内でも新米の店頭販売が始まっており、金沢市のスーパーでは、
5kgあたり4600円を超える価格で販売されました。これは前年の1.5倍にあたります。
また、東京都内の米販売店では、佐賀県産コシヒカリの玄米5kgが税込4600円で販売され、
前年の価格よりも1300円、約4割の値上がりとなっています。
千葉県産の新米も4000円を超える価格で出回っており、2024年と比較して1000円以上高くなっています。
備蓄米の影響は限定的 今後の価格動向は収穫量次第
今回の販売期限延長によって、消費者にとっては選択肢が一つ増える形となりました。
ただし、備蓄米が市場に出回ることで新米の価格が下がるかどうかについては、
米販売店などの関係者からは「それはない」との見方もあります。
都内の精米店では、「価格の上下は収穫量によって決まる」とし、
「平年以上に取れれば価格は落ち着くが、収穫量が少なければ今の高値が続く、またはさらに上がる可能性がある」と話しています。
今後は、各地の収穫状況や、販売された備蓄米の流通スピードが、消費者の実感としての米価格にどう反映されていくのかが注目されます。