5月5日は「端午の節句」。こいのぼりや兜飾りでお祝いするだけでなく、家族みんなで囲む「食卓」もまた、大切なイベントのひとつです。この記事では、端午の節句にぴったりなおすすめ料理を、定番・子ども向け・時短・祖父母との団らん・おもてなしの5つのシーン別にご紹介!
中学生でも簡単に読めるやさしい言葉で、楽しくわかりやすくまとめています。忙しいママにも、料理が苦手なパパにも、すぐに使えるアイデアが満載ですよ。
|
|
端午の節句に食べる定番料理とは?
柏餅の意味と地域による違い
柏餅は、端午の節句に欠かせない和菓子のひとつです。もちもちとした白いお餅に、甘いあんこが包まれていて、さらに柏の葉でくるまれているのが特徴です。この柏の葉には大切な意味があります。「柏の葉は新芽が育つまで古い葉が落ちない」という性質があり、「家系が絶えない」や「子孫繁栄」といった願いが込められているのです。
関東と関西では柏餅の中身に違いがあることをご存じですか?関東ではこしあんやつぶあんが主流ですが、関西では味噌あんが多く見られます。この味噌あん、ほんのり塩気があって甘さとのバランスが絶妙。ちょっと大人の味わいで、関西出身の方には懐かしい味として親しまれています。
柏餅はスーパーや和菓子屋さんでも手軽に購入できますが、最近では家庭で手作りする方も増えています。白玉粉を使えば、簡単にお餅風の生地が作れますし、子どもと一緒にあんこを包むのも楽しいイベントになります。手作り柏餅なら、好きなあんこや色をアレンジできるのも魅力ですね。
ちまきの歴史と現代風アレンジ
ちまきはもともと中国から伝わった風習で、厄除けや無病息災を祈るために食べられてきました。もち米を笹や竹の葉で包み、蒸して作るちまきは、その香りがよく、葉の殺菌作用もあり保存性が高いという利点もあります。端午の節句にちまきを食べることで、悪いものを遠ざけるという意味が込められているんです。
日本でも古くからちまきは食べられており、関西地方では特にポピュラーです。ただし、和菓子タイプのちまきと中華ちまきでは内容がまったく異なります。和菓子ちまきは、あんこ入りのお団子を笹で包んだもの。一方、中華ちまきは、味付けしたもち米に豚肉やシイタケなどを入れ、笹で包んで蒸しあげたボリューミーなおかず系。
最近では、炊飯器を使って簡単に作れる「なんちゃってちまき」レシピも人気です。もち米とお好みの具材を入れて、炊飯器で炊くだけ。おにぎりの形にしてから笹の葉やラップで包めば、見た目も立派なちまき風に。手軽さと見た目の華やかさから、忙しい家庭でも取り入れやすい料理となっています。
鯉のぼり料理で子どもが笑顔に!
鯉のぼりは、端午の節句を象徴する飾りですが、最近では「鯉のぼり」をモチーフにした料理も話題です。特に小さな子どもがいる家庭では、見た目がかわいく、しかも食べて楽しい鯉のぼり料理が大人気!
一番人気は「鯉のぼりおにぎり」。ご飯にのりやチーズ、ハムなどを使って、鯉のぼりの顔やうろこを表現します。子どもと一緒に作れば、お料理体験としても◎。彩りの良い食材を使うことで、栄養バランスも取りやすくなります。
また、パイシートを使った「鯉のぼりパイ」もおすすめ。中にカレーやハム&チーズを入れて、鯉の形にカット。表面に卵黄を塗って焼けば、サクサク香ばしい一品が完成します。お弁当やパーティーにもぴったりな華やかメニューです。
子どもが主役の端午の節句。鯉のぼりを食卓に取り入れることで、より記憶に残る楽しい1日になりますよ。
お祝いにぴったりな鶏の照り焼き
端午の節句は、子どもの成長を祝う日。そんなお祝いの席には、しっかりメインになる肉料理も欠かせません。特に「鶏の照り焼き」は、甘辛い味付けで子どもから大人まで大人気の一品です。
鶏もも肉を使えば、ジューシーでボリューム感もたっぷり。醤油、みりん、砂糖を合わせたタレに漬け込んで焼くだけで、ごはんが進む定番おかずが完成します。焼きあがったら、照りを出すためにもう一度タレを絡めて仕上げると、見た目も美しく仕上がります。
また、野菜を添えることで栄養バランスも整います。にんじんやブロッコリーなど、色とりどりの付け合わせを選べば、食卓がぐっと華やかになりますね。子ども用には小さめにカットして、食べやすくするのもポイントです。
鶏の照り焼きは冷めてもおいしいので、お弁当にもおすすめです。節句のお出かけやピクニックにも使える万能料理ですよ。
お吸い物に込められた願いと工夫
お祝いの席に欠かせない汁物といえば「お吸い物」。特に端午の節句では、あっさりとした味わいのお吸い物が人気です。具材には、縁起の良いものを選ぶとよりお祝い感がアップします。
たとえば「はまぐり」や「鯛」は、昔から縁起物とされてきた食材です。また、季節の野菜や、花型に抜いたにんじんなどを加えることで、見た目にも華やかになります。香りづけには柚子の皮や木の芽を添えるのもおすすめです。
簡単に作れるお吸い物としては、だしをしっかり取ったあとに、豆腐、わかめ、三つ葉などを入れるレシピが定番。和風の基本を感じられる味わいで、どんな料理とも相性がいいのが魅力です。
また、最近ではインスタントのだしパックや液体だしを使って、手軽に本格的な味を再現する人も増えています。手間をかけすぎず、でもきちんとした味を出したい時にはうれしいアイテムですね。
子どもが喜ぶ!カンタンかわいいレシピ集
鯉のぼりおにぎりの作り方
端午の節句の食卓に、ぱっと明るい雰囲気を添えてくれる「鯉のぼりおにぎり」。見た目が可愛く、子どもたちが喜んで食べてくれること間違いなしのメニューです。ご飯を好きな形に握り、のりやチーズ、野菜などで鯉のぼりの模様を作っていきます。工作感覚で楽しめるので、ぜひ子どもと一緒に作ってみてください。
作り方はとても簡単です。まずはご飯を棒状に成形して、鯉のぼりの胴体にします。白ごはんでもいいですが、鮭フレークやふりかけで色をつけるとさらに華やかになります。次に、のりでうろこ模様を作って貼り付けたり、チーズやきゅうり、にんじんなどを使って目や飾りをつけていきます。
うろこ部分には、薄焼き卵やハムを丸く型抜きして貼るのもおすすめ。カラフルで立体感も出て、食欲をそそります。目はスライスチーズに海苔を小さく切って貼るだけで簡単に再現できます。
おにぎりの下に葉っぱを敷いたり、旗のようなピックを刺せば、まるで本物の鯉のぼりのように。見た目が華やかなので、写真映えもバッチリです。お弁当にもぴったりで、遠足やイベント時にも活躍しますよ。
味は家庭の好みに合わせてアレンジ可能ですし、苦手な野菜も飾りにしてあげると食べやすくなります。楽しく作って、楽しく食べる。そんな「食育」の時間にもなる、端午の節句にぴったりの一品です。
ウインナー兜ピックの盛り付け術
端午の節句といえば「兜」が象徴のひとつですが、それを食卓に取り入れるなら「ウインナー兜ピック」がオススメです。お弁当やワンプレートのワンポイントとしても大活躍!見た目のインパクトは抜群で、子どもたちが大喜びすること間違いなしのアイデア料理です。
まず、用意するのは赤ウインナーとパスタ用のピックや爪楊枝。ウインナーを斜めに切って、上下のパーツを組み合わせて兜の形にします。火を通した後に、ピックで固定すれば兜の完成です。形を崩さずにきれいに仕上げるコツは、ウインナーを一度茹でてから成形すること。柔らかくなって扱いやすくなります。
さらに、チーズやのりで「兜の紋章」風の飾りをつけると、ぐっと完成度が上がります。ウインナーの赤、チーズの白、きゅうりの緑などを組み合わせることで、彩りも良くなり、お祝いムードが盛り上がります。
このウインナー兜は、おにぎりの横に添えたり、唐揚げや卵焼きの横にちょこんと置くだけで、プレート全体がぐっと華やかになります。子どもと一緒に「兜作り」を楽しむ時間も、節句の良い思い出になりますね。
簡単で時短、しかも材料費も少ないのに、こんなにインパクトのある飾りができるのは嬉しいポイント。ぜひ、お祝い料理のアクセントに取り入れてみてください。
色とりどりの野菜春巻き
「野菜が苦手…」という子どもも多いですが、見た目がカラフルで可愛ければ、興味を持って食べてくれることもあります。そんなときにぴったりなのが「色とりどりの野菜春巻き」。端午の節句の食卓をパッと明るくしてくれる、ヘルシーで嬉しい一品です。
作り方はとてもシンプル。春巻きの皮を半分に切り、好きな野菜を巻いて揚げるだけです。おすすめの具材は、にんじん、パプリカ、ほうれん草、とうもろこしなど。味付けは塩こしょうでもよいですし、カレー粉をほんの少し加えると子どもウケも抜群です。
中身が見えるように「生春巻き」風にするのもアリ。ライスペーパーを使えば、具材の色が透けて見えて、まるでステンドグラスのような美しさに。見た目にインパクトがあり、食卓を華やかに彩ってくれます。
また、ディップソースを添えると、さらに楽しさアップ。ケチャップやマヨネーズ、ヨーグルトソースなど、味のバリエーションをつければ飽きずに食べられます。自分で好きなソースを選べるのも、子どもにとっては楽しい体験になりますね。
食物繊維やビタミンがたっぷり取れて、見た目も楽しい。そんな春巻きは、端午の節句だけでなく、普段の食卓にも取り入れたい万能メニューです。
甘くてヘルシー!カボチャ団子
デザートにもおやつにもなる「カボチャ団子」は、野菜が苦手な子どもでもぺろりと食べてしまう優れたレシピです。ほんのり甘くて、もちっとした食感がたまらない一品。端午の節句の食後にぴったりの、ヘルシースイーツとしておすすめです。
材料はとてもシンプルで、かぼちゃ、片栗粉、砂糖だけ。かぼちゃはレンジで柔らかく加熱し、皮を取って潰します。そこに片栗粉と砂糖を加えて混ぜ、一口大に丸めます。あとはフライパンで軽く焼き目をつけるか、茹でてもOK。お好みで仕上げにきなこや黒蜜をかけると、より和風スイーツ感が出て大人も満足できる味になります。
また、色が鮮やかで目を引くので、プレートのアクセントにもぴったり。お祝い料理に並べれば、彩りと甘みでバランスの取れた食卓が完成します。さらに、冷めてもおいしいので、作り置きしておけばおやつや朝ごはんにも便利です。
栄養面でも優秀なカボチャ団子は、ビタミンAや食物繊維が豊富。小さい子どもにも安心して食べさせられるので、ママたちにも人気のレシピです。
かわいいピックや型抜きで飾り付けをすれば、見た目もさらに楽しく。ぜひ、節句のデザートに取り入れてみてください。
デザートに!柏餅風クレープ
和菓子の柏餅も良いけれど、ちょっと洋風にアレンジして「柏餅風クレープ」にするのも新鮮でおすすめ。もちもちのクレープ生地にあんこを包んで、柏の葉の代わりに緑のクレープで巻けば、まるで柏餅のような見た目に。子どもにも大人にも好評の、可愛いデザートです。
クレープ生地はホットケーキミックスでも簡単に作れます。牛乳と卵を混ぜて、生地を薄く焼くだけ。プレーン生地と、抹茶パウダーを混ぜた緑の生地を作っておけば、彩りも楽しめます。
包む中身はこしあん、白あん、つぶあんなど、好みに合わせてアレンジ可能。さらに、いちごやバナナなどフルーツを入れると、和洋折衷の楽しい味に変身します。子ども用には小さめにカットしたものを包めば、食べやすさもアップ。
柏の葉の代わりに、クレープ生地を葉っぱの形に切ったり、包み方を工夫することで見た目にも「柏餅っぽさ」が演出できます。完成したら、お皿に葉っぱ型のチョコソースや粉砂糖を飾ると、ぐっとおしゃれな印象に。
伝統的な和菓子の楽しさを残しつつ、新しい形で味わえる「柏餅風クレープ」。端午の節句の新しい定番になるかもしれませんね。
忙しいママ必見!時短で作れる節句料理
|
|
市販品を使った簡単ちまき風ごはん
端午の節句といえば「ちまき」が代表的な料理ですが、笹で包んで蒸して…という本格的な工程は忙しいママにはハードルが高いもの。そんなときにぴったりなのが、市販品を上手に使った「ちまき風ごはん」。味や見た目はちまきらしさをしっかり残しつつ、時短でパパッと作れるレシピです。
基本の材料は、レトルトの炊き込みご飯の素や、混ぜご飯の素を使うのがポイント。これにもち米やうるち米を加えて炊けば、もちもち感のあるちまき風ごはんが簡単に作れます。具材は鶏肉、ごぼう、にんじん、椎茸などが入った和風の味付けがベスト。
炊きあがったご飯は、おにぎりにしてラップでくるっと包むだけでも立派なちまき風に。さらに、100円ショップなどで売っているバランの葉や竹の葉風シートを使えば、見た目の完成度もぐっと上がります。
子どもと一緒に「包む係」をしてもらえば、食事の準備が楽しいイベントにもなりますね。冷凍保存も可能なので、前日に仕込んでおくこともでき、当日は温めるだけでOK。手間をかけずに伝統の味を楽しめる、忙しい家庭の心強い味方です。
「ちまき=手間がかかる」というイメージをくつがえす、時短&満足度の高いアイデアレシピ。ぜひ活用してみてください。
炊飯器で作る鶏とごぼうの混ぜご飯
炊飯器は忙しい日々の強い味方。材料を入れてスイッチを押すだけで、手間のかかる料理があっという間に完成します。端午の節句におすすめなのが「鶏とごぼうの混ぜご飯」。ほんのり甘辛い味付けがご飯にしみ込んで、子どもにも大人にも大好評の一品です。
使う材料は、鶏もも肉、ごぼう、にんじん、しいたけ。すべて細かく切って、軽く炒めてから炊飯器に入れると、旨みがより引き立ちます。調味料は醤油、みりん、酒、砂糖など。和風の基本的な味付けで、ご飯全体がほんのり甘く香ばしい仕上がりになります。
普通の白米と一緒に炊くことで、もちもちしつつも食べやすい食感に。上に彩りとして、錦糸卵や青ねぎをのせると、見た目にも華やかです。型抜きしたにんじんをトッピングすれば、節句らしい飾りにもなりますね。
余った分はおにぎりにして冷凍保存も可能。朝食やお弁当にも使い回せて便利です。「作り置き」できるという点でも、忙しい家庭には嬉しいレシピです。
手軽なのに豪華に見える。これぞ、節句料理の理想形。炊飯器ひとつで完成するこの混ぜご飯、ぜひ試してみてください。
ワンプレートで完結!バランスごはん
端午の節句のごちそう、いろいろ用意したいけど、準備も片付けも大変…そんなママの悩みを解決してくれるのが「ワンプレートごはん」。栄養バランスも見た目の華やかさもバッチリ、しかも洗い物が少なくて済むのが魅力です。
ワンプレートの基本構成は「主食+主菜+副菜+汁物(別添)」。例えば、鯉のぼりおにぎりを主食にして、鶏の照り焼きを主菜、野菜の春巻きを副菜に添えると、カラフルで節句らしい盛り合わせになります。食材の色に気をつけるだけで、自然とバランスが取れた献立になりますよ。
プレートの選び方も大切です。仕切り付きのプレートを使えば、味が混ざらず見た目もきれい。100円ショップや雑貨店で手軽に手に入ります。小さなカップやピックを活用して盛り付ければ、まるでカフェごはんのような雰囲気に!
時間がなければ、冷凍食品やレトルト商品を上手に活用するのもポイント。すべてを手作りしようとせず、ラクに・楽しく・見た目もGOODな食卓を目指すのがコツです。
お祝いだからといって無理をしすぎないで、家族が笑顔になる「ちょっと特別なワンプレートごはん」を作ってみてくださいね。
レンジでOK!柏餅もどき
柏餅を手作りしたいけど、蒸し器もないし時間もない…。そんなときに大活躍するのが「レンジで作れる柏餅もどき」。材料さえそろえば、10分ほどでモチモチのお餅スイーツが完成します。しかも本格的な味わいで、節句の雰囲気をしっかり楽しめる一品です。
使うのは白玉粉、砂糖、水、そしてお好みのあんこ。まず白玉粉に水を少しずつ加えて練り、生地をラップに包んでレンジで加熱します。途中で一度取り出して練り直し、さらに加熱すれば、もちもちの生地が完成します。それを小さくちぎって広げ、あんこを包むだけ。
包んだら、柏の葉の代わりに緑の大葉や、竹の葉風のラップで包むと雰囲気が出ます。もちろん本物の柏の葉を購入して使ってもOK。スーパーやネットでも手に入ります。
レンジで簡単にできるので、子どもと一緒に「包む体験」を楽しめるのもポイント。ちょっとした実験みたいで、ワクワク感も倍増します。洗い物も少なくて済むので、後片付けもラクラク。
忙しい日でも、ほんの少しの時間と工夫で、しっかり季節感を楽しめる「柏餅もどき」。手軽だけど、気持ちのこもった一品になること間違いなしです。
使いまわし可能な作り置きおかず
平日が忙しくて料理の時間が取れない…そんなときは「作り置きおかず」で乗り切りましょう。端午の節句に使えるメニューでも、アレンジ次第で何日も使える便利なレシピがたくさんあります。冷蔵・冷凍保存がきいて、お弁当にも応用できるものがおすすめです。
たとえば、「鶏の照り焼き」は大量に作っておけば、ごはんにのせて丼にもなるし、翌日はおにぎりの具にも活用できます。「煮しめ」も、冷めてもおいしいので常備菜にぴったり。味がしみ込んで、日に日においしさが増します。
「ひじきの煮物」や「切り干し大根の煮付け」などの和風おかずもおすすめ。これらは冷凍も可能で、必要な分だけ解凍して使えるのでとっても便利です。忙しい朝のお弁当作りにも大活躍します。
また、彩りを考えて、にんじんやピーマン、パプリカなどを加えておくと、お祝い感もアップします。タッパーにきれいに詰めておけば、冷蔵庫を開けるたびにテンションも上がりますよ。
忙しいママほど、「手を抜きつつ、ちゃんと見える」工夫が大切。作り置きを活用して、節句の日にも余裕のある食卓を演出してみましょう。
祖父母と一緒に楽しむ伝統料理
一緒に包もう!手作りちまき
ちまきは、もともと無病息災を願う食べ物として端午の節句に食べられてきました。地域によって形や味は異なりますが、手間ひまをかけて包む工程こそが、ちまきの醍醐味でもあります。そこでおすすめなのが、祖父母と一緒に手作りする「包む」体験。世代を超えて楽しめる時間になります。
もち米は前日から水に浸しておくと、当日スムーズに調理できます。具材には、豚肉、干ししいたけ、たけのこなど、味がしみやすいものを使うと本格的な味わいに。すべての具材を炒めて味付けしたら、もち米と混ぜて、笹の葉や竹の皮で包み、紐でしっかりと結びます。
蒸し器で蒸す時間は少しかかりますが、その間に家族で団らんしたり、おしゃべりを楽しめるのもこの料理のいいところ。祖父母が子どもたちに「昔はこうやって包んでね…」と伝える姿もまた、家族の絆を感じさせてくれる大切な瞬間です。
また、ちまきを包む作業は不器用な手でも楽しめますし、多少形がいびつでも、それが手作りならではの良さ。完成したら、みんなで「できたね!」と達成感を味わいましょう。手間がかかるからこそ、心に残る、そんな料理です。
おばあちゃんのレシピ再現!煮しめ
日本の伝統的な家庭料理といえば「煮しめ」。根菜やこんにゃくなどをだしでゆっくり煮込んだこの料理は、お祝いごとの席にもよく登場します。端午の節句でも、昔ながらの味を楽しみながら、世代を超えて受け継がれる味を再確認するのにぴったりの一品です。
煮しめの魅力は、野菜のうまみがしっかりとしみ込んでいるところ。にんじん、ごぼう、れんこん、しいたけ、こんにゃくなど、どれも素朴ながらしっかりした存在感があります。調味料は、だし、しょうゆ、みりん、砂糖といったシンプルな組み合わせで、食材本来の味を引き出します。
祖母世代の味を再現するには、「火加減」と「時間」がポイント。弱火でコトコト煮ることで、味がじんわりと中まで染み込みます。冷めるときにさらに味がしみるので、前日に作っておくのもおすすめです。
また、にんじんを花型に抜いたり、れんこんを飾り切りにすることで、見た目も華やかに。お祝いの日にぴったりの一品になります。おばあちゃんの「ひと手間」を聞きながら一緒に作る時間もまた、何よりのごちそうです。
思い出の味を再現しながら、家族みんなで笑顔になれる「煮しめ」。節句の日の食卓に、ぬくもりを添えてくれる料理です。
健康を願うよもぎ料理
端午の節句といえば「菖蒲(しょうぶ)」や「よもぎ」が象徴的な植物。特によもぎは古くから健康を守る薬草として重宝されてきました。現代でも、よもぎを使った料理や和菓子は、香り豊かで春らしい風味が楽しめることから人気です。
代表的なよもぎ料理といえば「よもぎ団子」。つぶしたよもぎの葉を白玉粉や上新粉に混ぜて作るこの団子は、鮮やかな緑色と独特の香りが特徴です。こしあんを包んだり、きなこをまぶしたりと、バリエーションも豊富。蒸したての団子はふわっと香りが立ち、春の訪れを感じさせてくれます。
また、よもぎの天ぷらもおすすめ。新芽の柔らかい部分を使えば、サクサクで香ばしい一品に。抹茶塩などを添えると、おしゃれなおもてなし料理にもなります。
近年は、よもぎ入りのパンケーキや蒸しパンなど洋風レシピも登場しており、子どもにも食べやすくアレンジが可能です。スーパーや道の駅などで手軽によもぎが手に入る春の時期に、ぜひ挑戦してみてください。
健康を願う心と、自然の恵みをいただく気持ちを育てる「よもぎ料理」。世代を問わず楽しめる、春のごちそうです。
鰹のたたきで季節を感じる
5月といえば「初鰹(はつがつお)」が旬を迎える時期。鰹のたたきは、さっぱりとしていながらも旨味があり、端午の節句の特別なごちそうとしてもおすすめの料理です。特に祖父母世代には馴染みが深く、懐かしい味わいとして喜ばれること間違いなしです。
鰹のたたきは、表面だけを強火で炙ったあと、冷水で締めてスライスするのが基本。最近ではスーパーで炙った状態のものがパックで売られているので、手軽に楽しめるのも魅力です。
薬味には、にんにくスライス、青ねぎ、みょうが、大葉など、香味野菜をたっぷりのせると香りが引き立ちます。ポン酢をかけてさっぱりいただくのが定番ですが、しょうが醤油でいただくのも美味です。
お祝いの席には、色鮮やかな器に盛り付けて、少し豪華に演出するとより華やかになります。副菜としても、メインに近い存在感があるので、和風の献立によく合います。
季節感を楽しみつつ、家族の健康を願う意味でもぴったりの「鰹のたたき」。祖父母と一緒に「今が旬だね」と会話が弾む、そんな一品をぜひ取り入れてみてください。
懐かしい味!甘酒と和菓子
端午の節句の食後やおやつタイムにぴったりなのが「甘酒と和菓子」の組み合わせ。どこか懐かしくてほっとする味わいは、祖父母世代には特に喜ばれます。しかもノンアルコールの甘酒なら、子どもから大人まで一緒に楽しめる優しいドリンクです。
甘酒は、米麹を使ったタイプがおすすめ。自然な甘さととろっとした口当たりが特徴で、体にも優しく、栄養価も高いです。温かくして飲むのはもちろん、これからの季節には冷やしても美味しく、さっぱりとした味わいが楽しめます。
和菓子には、柏餅やちまき、よもぎ団子のほか、季節の上生菓子などを合わせて。見た目が美しく、器やお皿に工夫をすれば食卓が一気に華やぎます。あんこが苦手な子どもには、フルーツ入りの寒天ゼリーや抹茶プリンなども◎。
また、甘酒を使ったアレンジレシピも人気です。例えば、甘酒入りのパンケーキや、ミルクと合わせたドリンクなど、洋風アレンジも試してみると新しい発見があります。
お祝いの締めくくりに、やさしい甘さと和の心を味わえる「甘酒と和菓子」。家族みんなでほっとする時間を共有できる、節句らしいティータイムです。
おもてなしにも使える映えるレシピ
鯉のぼり寿司ケーキ
端午の節句のおもてなしにぴったりなのが、見た目も華やかで写真映えする「鯉のぼり寿司ケーキ」です。子どもが喜ぶだけでなく、大人も「わあ!」と驚くインパクトがある一品。特別な日を彩る主役級のレシピです。
作り方は意外と簡単で、酢飯を型に詰めて層を重ねていくだけ。牛乳パックを切って型にするのもOKです。間にスモークサーモンやツナマヨ、炒り卵などの具材を挟むことで、味にもバリエーションが生まれます。
仕上げには、表面にスライスチーズやハムを使って鯉のぼりの「目」や「うろこ」をデコレーションします。うろこ部分は、薄焼き卵を型で抜いたり、にんじんやきゅうりの輪切りでも代用できます。カラフルな具材を使うことで、子どもが喜ぶ見た目になりますよ。
プレートに盛りつけた後は、周りに桜でんぶや青じそを添えると、彩りがぐっと引き立ちます。鯉のぼりのしっぽの部分を波模様にして、動きのあるデザインにするのもおすすめです。
お祝いの日だからこそ、ちょっと特別な見た目と味を楽しめる「寿司ケーキ」。作る工程も楽しいので、家族でワイワイ作ればさらに思い出深い一皿になります。
ミニお重で彩るお祝い膳
お祝い感をしっかり出したいときに活躍するのが「ミニお重」。お正月だけでなく、端午の節句にもぴったり。少しずつ色んなおかずを詰めることで、見た目も美しく、栄養バランスもばっちりなスタイルです。
1段目には、おにぎりやいなり寿司などの主食を詰め、2段目には唐揚げ、卵焼き、野菜の煮物などの主菜・副菜を並べます。最後の段には、フルーツや和菓子、ミニサイズのデザートを入れると、お子さまも大満足のお重になります。
ポイントは「カラフルさ」と「高さ」。赤・緑・黄を意識した食材選びをすると、見た目に統一感が出て写真映えもします。カップや小さな仕切りを使って立体感を出すと、まるでプロが詰めたような完成度に!
また、100円ショップなどでも買える小さめのお重箱を使えば、手軽にスタートできます。子ども一人ひとりに専用のお重を用意して「マイ重」にしてあげると、特別感が倍増しますよ。
家族全員でお祝いする日にぴったりの、気持ちが伝わるスタイル。作るのも食べるのも楽しくなる、映えるおもてなしスタイルです。
花形ちらし寿司
ひと目で「お祝いごとだ!」と感じさせる料理といえば「ちらし寿司」。それをもっと可愛く、華やかにアレンジしたのが「花形ちらし寿司」です。丸く握った寿司ご飯に色とりどりの具材を花びらのように並べれば、食卓に春の花が咲いたような演出ができます。
土台となる酢飯は、小さなお椀などで形を整えておくと綺麗に仕上がります。その上に、錦糸卵、サーモン、きゅうり、桜でんぶなどをバランスよく盛り付けると、花の形に見えてきます。海苔で花の中心を作ると、よりリアルな印象に。
花びらの色を変えることで、複数の「花寿司」を並べて楽しむこともできます。たとえば、サーモンでオレンジ系、マグロで赤系、玉子焼きで黄色系といった感じで、色ごとのバリエーションを楽しめるのも魅力。
子どもには「どの花にする?」と選ばせる楽しみを加えたり、一緒に盛りつけを体験させてあげても良いですね。手で簡単に食べられるサイズなので、パーティーや持ち寄りにも向いています。
見た目にときめいて、食べて美味しい。花形ちらし寿司は、端午の節句のテーブルをぐっと華やかに彩ってくれる名脇役です。
季節の天ぷら盛り合わせ
端午の節句の食卓に「季節感」と「彩り」を加えてくれるのが、天ぷらの盛り合わせ。さくさくとした衣の中に、春野菜のうまみがぎゅっと詰まっていて、見た目も華やか、食感も楽しい一品です。
春のおすすめ食材は、タラの芽、ふきのとう、スナップエンドウ、アスパラ、エビ、かぼちゃなど。野菜だけでも彩りが豊かなので、お祝いの席にぴったりです。下ごしらえはシンプルで、衣を薄めにして揚げるのが軽やかに仕上げるポイント。
揚げたてをそのまま出すのが理想ですが、冷めてもおいしいように工夫したいなら、天つゆだけでなく抹茶塩やカレー塩など、複数の味つけを用意すると良いでしょう。特に子どもにはケチャップやチーズソースも喜ばれます。
盛り付けは、高さを出すように盛ると見た目に豪華さが出ます。ワックスペーパーや和紙を敷いてから盛ると、プロっぽい印象にもなりますよ。
油を使う料理ですが、野菜をたっぷり使えば意外とヘルシー。お祝いムードを高めつつ、春の味を楽しめる天ぷら盛り合わせ。家族やゲストとの会話も弾む、おすすめの一品です。
抹茶プリンで和のスイーツを
食後のデザートに、ほろ苦くてなめらかな「抹茶プリン」はいかがでしょうか?甘すぎず、大人にも子どもにも人気の和風スイーツ。お祝い料理の締めくくりにふさわしい、上品な一品です。
基本の材料は、牛乳、生クリーム、砂糖、ゼラチン、抹茶パウダー。すべてを火にかけて混ぜ、冷やすだけで簡単に作れます。なめらかな口当たりを出すには、しっかりとこす工程がポイント。茶こしなどで一度漉してから容器に入れると、プロのような仕上がりに。
トッピングには、ホイップクリーム、黒蜜、あんこ、白玉などを合わせると、一気に「和風カフェ」風になります。透明のグラスや和風の小鉢に盛りつければ、見た目にも季節感が出て、ゲストからも喜ばれます。
子どもには甘さを調整したり、フルーツを添えて華やかさをプラスするのもおすすめです。食後でも重たくならず、さっぱりとした後味が好評です。
簡単なのに高級感のある「抹茶プリン」。普段のおやつとしても、おもてなし用としても活躍する万能スイーツです。
まとめ
端午の節句は、子どもの健やかな成長を願い、家族みんなでお祝いする特別な日です。この記事では、伝統的な料理から子どもが喜ぶ可愛いレシピ、忙しい日でも作れる時短料理、祖父母と一緒に楽しむ和の味、そしておもてなしにも映える華やかな一皿まで、幅広いアイデアをご紹介しました。
料理はただの食事ではなく、家族の絆を深める大切な時間でもあります。手間をかけて作るものから、市販品を上手に活用した時短レシピまで、今の生活に合ったスタイルで楽しむことが大切です。
大人から子どもまで、みんなが笑顔になれるような「おいしい記憶」を作って、今年の端午の節句を心に残る一日にしてくださいね。
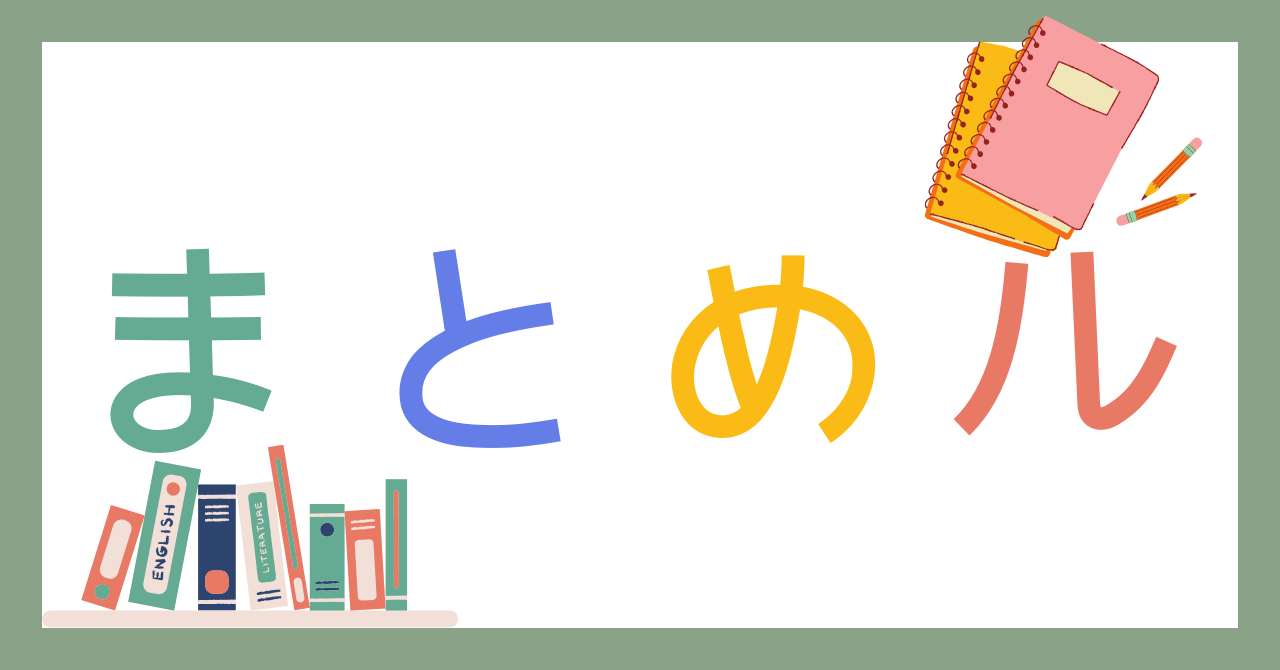
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/37cbe465.48ded58f.37cbe466.04ec2511/?me_id=1263613&item_id=10003251&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-ningyohonpo%2Fcabinet%2Fgogatu%2Fnew5premomini-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46d46caa.b6c20cac.46d46cab.372744ed/?me_id=1225237&item_id=10008995&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbutuendo%2Fcabinet%2Fcabinet31%2Feng-0020-00r.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
